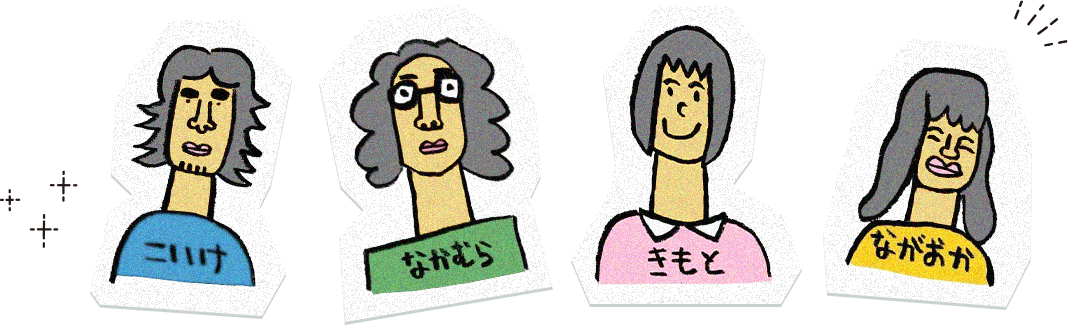長年愛する器にするために。
2025.09.03
こんにちは。クラフェス事務局のナガオカです。みなさん、突然ですが「ハスカップ」という食べ物をご存知ですか? 北海道出身の私にとっては馴染みの果実なのですが、北海道の特産品だということを今日はじめて知りました。というのも、今日は北海道蚤の市でお世話になった長沼町(夕張郡)の方が手紙社を訪ねてきてくれて、お土産に焼菓子をいただきました。その中にハスカップを使用したお菓子があったのですが、ナカムラが「ハスカップって何?」と質問をしているところを聞いて、本州にハスカップが存在しないということを知り、衝撃を受けました。ハスカップは、北海道の希少な果実でアイヌ語の「ハシカプ(枝の上にたくさんなるもの)」が語源です。ブルーベリーのような鮮やかな青紫色で、強い酸味が特徴です。ジャムやソフトクリームが美味しいので、北海道に行かれる際はぜひ召し上がってみてください! みなさんのお住まいの地域に特産品があれば、Instagramのコメント欄などでぜひ教えてくださいね。
さて、本日は前々回に私が投稿した記事の続きを書こうと思います。「まだ読んでないよ!」という人はぜひ読んでみてくださいね。前々回の投稿では、京都で開催していた陶芸家・小谷田潤さんの個展を訪れ、改めて器を使う楽しさを体感したエピソードをお届けしました。小谷田さんの個展で購入した器を、実際に使うために準備をしてみたその感想を綴っていきます。今回もクラフト初心者全開の記事になりそうですが、優しく見守ってもらえると嬉しいです。
まずは購入した器のご紹介。私が購入したのは、顔の大きさくらいある大きな平皿。今回の個展のテーマが「シチリア島」だったことから、ベースの色はクリーム色、ふちの色はベージュで、まるでレモンを輪切りにしたかのような配色。聞けば、個展だけのオリジナル作品とのこと。ずっと指でなぞってしまいたくなる、リムにかけてのなだらかな曲線に“とぅるっ”とした表情。ふちのベージュがアクセントとなり、長年使い続けてもきゅんと胸がときめいてしまうような一枚です。実はもう1点購入したい黄色の平皿があったのですが、連日、京都の美味しいご飯を食べすぎて財布の中身がすっからかんだったので、泣く泣く我慢しました。なので、「東京クラフトフェスティバルでぜひご本人から購入したい!」と意気込んでおります。

話を戻して、この平皿を購入した際にギャラリーのスタッフさんから、小谷田さんの器にプラムの乗った写真が印刷された1枚のカードが渡されました(このカード、小谷田さんの盟友でもある写真家でグラフィックデザイナーの岡崎直哉さんによるものと聞きました!)。自宅に帰ってからその裏面を見ると、器のお手入れ方法と小谷田さんからのメッセージが。優しいお気遣いにきゅんとしながら、長年この平皿を愛していくため、早速書かれていた、陶器を使い始めるための準備「目止め」を試してみました。
目止めにはまず米とぎ汁を使います。片栗粉や小麦粉などを溶かした水でも良いそうです。お米をとぎ、土鍋で炊いている間に、その横で米とぎ汁を軽い糊状になるまで火を通します。ぐつぐつとその液体が沸騰する様子を眺めていると心が落ち着きました。どれくらい沸騰させればいいのかわからず、鍋の半分ほどまでいれていたはずの液体が残り1センチくらいになるまで蒸発させてしまいました。ですが、ちょっと粘り気のある液体になりました。そうしてできた糊状のそれを平皿に流し込み、1〜2時間ほど置いておきます。どんな風になるのだろうと、ワクワクしながら待つ時間も至福の時でした。置いたあとは、お皿を洗い、拭いてあげると無事目止め完了です(きちんとできているはず)!
こうすることで、目の粗い土でできた陶器に水が染み込みにくくなり、料理の染みや臭いがつきにくくなるんですね。時間をかけてお手入れした平皿は、さらに“とぅるっ”が増したように見え、より愛着が湧いてきて「れも太郎」という名前まで付けてしまいました(ナガオカは愛着の湧いたものに名前をつける癖があります)。そして、れも太郎に無事目止めができたことが嬉しく、キッチンで1人きゃっきゃとはしゃいでいました。
今回、小谷田潤さんの個展を訪れたことで、数ある器の中から自分にぴんとくる器を選び、自宅でお手入れをするところまで、すべての体験が豊かで、ゆっくりと時を進めていくような、生活の細部がクリアに見えてくるような感覚になりました。東京クラフトフェスティバルに来てくださるみなさんも、こんな風に会場での思い出を、家に帰ってからもより深めていくのだろうなとしみじみ思いました。クラフト好きのみなさんの器の楽しみ方やお手入れ、それの愛し方をぜひ知りたくなっちゃいました。そんな大好きな作品を持ち寄って語る会ができたら面白そうだな〜と妄想を膨らませながら、今日の記事は綴じさせていただきます。作り手たちの人生や思いの上に、自分の思い出や愛を乗せていく。そんな生活を今後もしていきたい。そう思わせてくれる作家の皆さん、その作品の数々に感謝の気持ちでいっぱいです。それではまた。