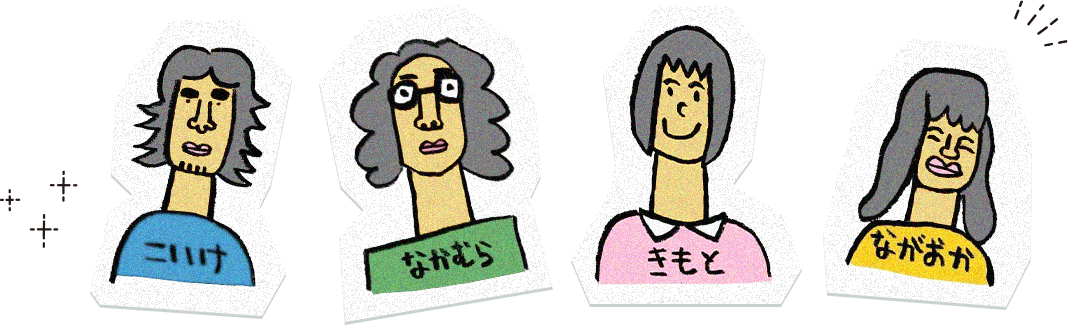クラフト初心者の私でも一端を覗ける作家の人生
2025.08.21
こんにちは! 東京クラフトフェスティバル事務局、ナガオカです。北海道札幌市出身、手紙社歴4ヶ月の新人です。好きな食べ物は牛タン。レモン汁をたっぷりかけて食べる派です。今年4月に手紙社の「紙博」を開催した仙台で、肉厚ジューシーな牛タンを堪能できて幸せでした! 今私は、千手観音のようにマルチタスクをこなすリーダー・コイケ、面倒見の良いムードメーカー・ナカムラ、「本当に年下?」と思うほどしっかり者のキモトの3人と一緒に、クラフェスの企画・運営に奔走しています。私はまだまだ未熟者ですが、少しでも早く戦力になれるよう、日々奮闘中です! 目指せ一人前!
さて、自己紹介はこれくらいにして、「クラフェスだより」がいよいよ始動しましたね。クラフェス事務局メンバーが各々クラフト作家やクラフトへの愛を語る場所。私は、たくさんの人の目に留まる場で自分の思いや考えを綴る文章を書くのは初めてなので、正直書いている今もずっとドキドキしています。でも、クラフト初心者として感じたことを、素直にお伝えできたらと思います。
私は、学生時代から器や生活雑貨が好きで、よく街中の雑貨店を巡っていました。ただ、当時は大量生産のプロダクト製品ばかりを手に取ることが多く、作家が手がけた陶器やガラス、布作品などクラフトになかなか触れる機会がありませんでした。「なんだか壊しちゃいそう」「私にはまだ早いかも」と、どこかで距離を感じていたんです。今、振り返ると“クラフト”という言葉自体にあまり馴染みがなかったのかもしれません。それから手紙社に入って4ヶ月。クラフトイベントで作家さんの作品を間近で見たり、お話しを伺ったり、先輩たちの考えに触れる中で、少しずつ世界が開けていくのを感じました。そしてついに、私にとってのお気に入りの作品に出会うことができました。最初は少し背伸びするような気持ちで手に取った作品の数々は、毎日使ううちにだんだんと生活に馴染み、今では暮らしの一部となっています。
ふと、クラフトのことを思い浮かべると、私の中に“音”が聞こえてくる気がします。「トントントン」「カンカンカン」「ぺたぺたぺた」。静かな工房の中で、人の手から生み出される音の数々です。クラフト作品にもその背景には必ず”人”の存在があります。全て人の手で、ひとつずつ、丁寧に作られている。クラフトにはその人の生き様だったり、作品を手がけた時の感情だったりがたっぷりと込められているようで、私はそこに一番魅力に感じています。そう考えると、同じ素材でも作家さんによって作風は全く違いますし、同じ作家さんの中でも、制作時期や心の状態によって、作品の雰囲気が変わってくるのだろうな、ということが想像できてきました。クラフトを見ている時、私たちは作り手の人生を見ているのだと感じます。

あるクラフトイベントで、手紙社でも度々お世話になっている廣田哲哉さんのブースを訪れました。不思議な“いきもの”たちが集うその空間で、廣田さんがこう話してくれました。「気持ちが落ち込んでいる時期の作品の顔は、ちょっとグロデスクな感じになってるんです。」その時、感情がそのまま作品に宿るなんて、なんて面白いんだろうと思いました。作家さんがどんな気持ちでこの作品を生み出したのか、作品と対話し、作家さんの人生を想像する楽しさを知りました。作品に気持ちが乗っちゃうなんて、機械にはできないことです。その日、私は廣田さんの作品をお迎えしました。おどけた顔をしたクマのような“いきもの”のカード立て。「どんな気持ちで作られたのだろう。」と想像を巡らせながら、毎日スマートフォンを立てるのに使っています。その人の想いに共感し、自分の生活に取り入れる。作家の人生を受け入れて、自分の暮らしと調和させていく。クラフト作品を暮らしに取り入れるってそういう営みなのかもしれません。
工場でつくられる製品も、効率的に生み出されたからこその美しさがあると思います。ですが、これらを想像した時、「ウィーン」「ガシャンッ」といった機械音と工場でプレスされて、レーンに流されているような無機質な情景が頭の中に浮かび上がります。そこには“誰かの人生”が見えてくることはあまりありません。対して、作家の手から生まれた作品を暮らしに迎え入れることは、その人の生き方や想いのかけらを、自分の生活の中にそっと招き入れることなのだなと、私は思うようになりました。
東京クラフトフェスティバルは、十人十色の人生と出会える場所。作り手の言葉を聞いて、その人の人生に少し触れて、その背景にあるストーリーを感じることで、自分の暮らしにそれを迎え入れ、豊かになる。私はまだまだ、クラフトの世界を知り始めたばかりですが、これからももっと多くの作家さんと出会い、そしてその向こうにある人生に触れていきたいと思っています。