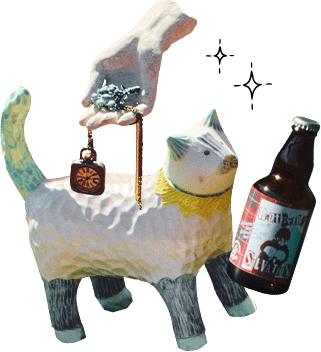


粕谷修朗
MAP/122

千葉県鴨川の山の中、自分で築窯した穴窯で近隣の山林で伐採された原木を割って薪を作り、窯を焚いています。松やマテバシイ、センダンなど房総らしい土地の木が灰となって、土に振りかぶり生まれる色合いに惹かれています。それと同時に火の動き次第の3日3晩の中、まったく同じ作品にはならない、そんなコントロールしきれない穴窯の難しさや愉しさを日々ひしひしと実感しています。また、穴窯の作品だけでなく、独立時からの電気ガス窯と両輪で作品も作ります。窯から出る灰を使って調合する灰釉や自然釉の作品、粉引き、焼き締めなど、いろんな表情で、皿、飯椀、茶器や花器を制作しています。「工房から見える山の景色が器に映しだされたら」。そんなことを思いながら作っています。薪の窯で生まれ一つひとつ違う表情の器たちを会場でぜひ手に取ってみていただけたら嬉しいです。

「湯呑と茶托」原土に含まれている鉄分が、焼成する過程で黒く浮き出して表情を作っています。お茶が美味しく見える粉引と白ぽい灰釉の2種。

「土瓶」窯の中でうっすらと灰が振りかぶって色と表情を作ります。どれも1点ものですので手に取って選んでいただきたいです。弦は真鍮です。

「灰釉皿」薪窯で焼成した灰釉皿は、乳白色が美しいです。直径21cm。

「菱形珈琲カップ」ろくろの上で指先だけで形を作っています。シンプルな見た目以上にじっくりと時間をかけて挽いていきます。粉引と灰釉の2種。

「灰釉花形皿」松の木灰を調合して作った灰釉がきれいな色を出す、型物の皿。鮮やかな野菜や果物、デザートにも。

「灰釉高台皿」刺身やチーズ、デザート、想像以上に使い道が多い高台皿。直径17cm。

「鉢」薪窯の中でかぶった灰が溶けて表情を生み出した自然釉の鉢。一点ものです。直径16.5cm。

「一輪挿し」粉引から灰釉、焼き締めと、色も形もいろいろの一輪挿し。

「茶壺と茶杯」台湾へ毎年訪れる中で制作するようになった中国茶用の茶器。他にも数種あります。茶葉の大きなほうじ茶にも使えます。