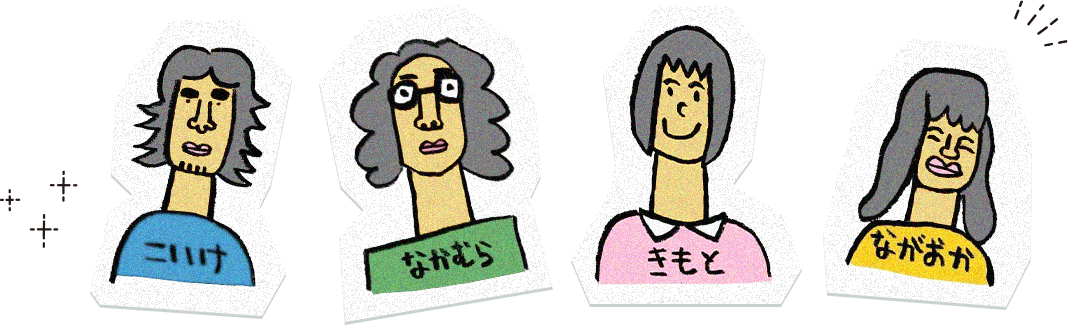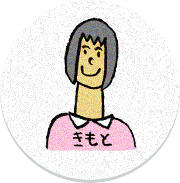初めまして。私とクラフトについて聞いてください。
2025.08.19
みなさま初めまして。クラフトフェスティバル実行委員会、手紙社のキモトと申します。こうして、クラフェス(東京クラフトフェスティバル、気軽にこう呼んでください!)を心待ちにしてくださっているみなさんに向けて、思いを綴る機会を持てるだなんて、喜びの気持ちでいっぱいです。
イベント主催者として、私たちがどんな思いを持っているか、みなさんへどんな時間を届けたいか、内に秘めたものを出す機会があったらいいなと考えていたのです。これから、今どんなことをしているか、今何を思っているか、隙あらば更新していきますので、「あ、キモト今日記事上げてるな」と注目していただけたら嬉しいです。

まずは、簡単に自己紹介をさせていただきます! 10月生まれのO型、好きな食べ物は白米です(出身は米どころ新潟!)。米と日本酒にはうるさいです。各地の日本酒が楽しめるご飯屋さんを探しては、足を運んでおります。最近は、我らが「TEGAMISHA BREWERY(クラフェスにも出店しますよ!)」のお店でクラフトビールを極めようと、日々新メニューの中で気になったものを味比べするのが楽しみのひとつ。同じ味覚を持つ人がいたら、嬉しいです!
さて、自己紹介はこれくらいにしておいて、ここでみなさんに質問です。みなさんにとって、‟クラフト作品”とはどんな存在でしょうか? 急な方向転換ですみません。でも、私が今日みなさんにクラフトとは、というお話をさせていただく上でどうしてもお聞きしたいのです。クラフト作品は作り手により全く特色が違う、見せる世界が違うものであります。作家それぞれの思いが込められたものであることは間違いないのですが、私は担い手(作品を買う人)の元に渡ることで、作品はさらに意味を持つと考えています。例えば、ある陶芸作家により、一枚のお皿が作られました。丹精と真心が込められて完成しました。そのお皿を‟どんな思いで”、‟誰が持つか”で、このお皿の在り方は無限に広がると思いませんか? ある人のもとでは、常に食卓を飾る、毎日心を満たしてくれるお気に入りの一枚となる。またある人のもとでは、ディスプレイとして大切に飾られ、見る度に心が癒される存在となる。お皿一枚で生まれるストーリーは、たくさん存在し得るのだと思います。1つの作品が、手に取った人によって全く違う運命を辿ることになる。担い手によって、さらに表情が付けられる。なんてロマンに溢れているんだろう! そう思いませんか? 作り手によって刻まれたストーリーは、様々な人に手に取られた後にも紡がれる。作って終わりではなく、買うだけでもない、‟もの”を超えた世界に1つだけの作品への奥深さに、心を震わされる。これこそが、クラフト作品の醍醐味であると私は考えます。

私が生まれて初めて自分で手にしたクラフト作品は、風鈴でした。それは私がまだ保育園に通っていたときの話です。ある日地元の神社に参拝に行った際、夏祭りに向けて準備が行われていました。飾りつけや出店の準備が行われる中、本殿の前に、ガラス職人の方によって作られた色とりどり様々な種類の風鈴が、竹の枠組みから吊り下げられていました。当時年齢一桁の私には、夏の日差しでキラキラと輝く風鈴のガラスが、宝石を見ているように綺麗でたまりませんでした。夢中になって見ていたら、職人の方が側に来て、「綺麗かい?」と私に話しかけてくださいました。私は幼いながらにいかに美しいかを説明しました。話を聞いた後に、職人さんが桜色の風鈴を1つ竹から外し、私にくださったのです。しかも、風鈴を仕舞うことができるようにわざわざ木箱も用意してくださいました。私は信じられないくらい嬉しくて、その日ずっと風鈴を木箱に入れたまま抱きしめていました。綺麗な風鈴を貰えたことが嬉しかったことはもちろんなのですが、何よりも一つひとつ手作業で作品を作っている方が、なんの見返りも求めずに、ただただ優しさを形として渡してくれたことに、心から感動したのです。当時の私には、ここまで深く考えが至っていなかったとは思いますが、大人になった今、当時の自分の気持ちを理解することができました。その風鈴の色合いや風合いからは、職人の方の人柄がとても良く出ています。今でもその風鈴は大切に手元にあります。そして先ほどの担い手に渡った話しに繋がるのですが、私は風鈴を夏以外でも使っています。人への思いやりを感じたときや、何か物事に迷ったときに、そっと風鈴を出して、涼しげな音を聞き、心の拠り所にしています。
人の手から生み出されたものは、誰かの心の源になる。原動力になる。そんな作品を生み出す作り手、そして一生ものを探す担い手が集まる場、それが、私の考える「東京クラフトフェスティバル」の理想です。誰かの将来が変わるかもしれない作品との出会いが生まれるイベントを開催できること、心から誇りに思います。開催日がみなさんにとって最高の日となるよう、イベントまでの日々を紡いでいきます。どうぞよろしくお願いします。また次の投稿でお会いしましょう。